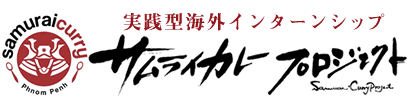「インターンに参加すべきか」——就活が近づくと、誰もが一度は悩むテーマです。まわりが参加していると不安になる一方、「本当に必要なの?」という疑問も残るはず。この記事では、就活とインターンの関係を冷静に整理し、自分に合った判断ができるよう、制度の仕組みや参加率、経験の活かし方まで専門家目線でわかりやすく解説します。
インターンに参加すべき?迷う就活生への答え

就活を始めたばかりの学生が最初に悩むことのひとつが「インターンに参加するべきかどうか」です。SNSや周囲の話を聞くと「インターンに行っていないと内定が取れない」といった不安を感じるかもしれません。しかし実際には状況は一様ではなく、参加していない学生も多くいます。インターン参加の現実と、得られること・得られないことを冷静に整理し、就活にどう向き合うべきかを考えてみましょう。
実際はどう?「行っていない人」も多い現実
文部科学省と厚生労働省の調査によると、大学3年生のインターン参加率は約60%程度とされています。つまり、約4割の学生はインターンに参加していないということです。「みんな行っているように感じる」のは、声が大きい人たちが目立つだけなのかもしれません。実際、最終的に内定を得ている学生の中にも、インターンに参加していなかった人は一定数います。
とある私立大学の学生は、授業やサークル活動を優先してインターンには一度も参加せずに本選考に臨みましたが、地元企業2社から内定を獲得しました。その理由は「自己分析と企業研究をしっかりやったから」。つまり、インターンは「必須」ではないが、代わりに準備の工夫が必要というわけです。
ただし、外資系やベンチャー企業の一部では、インターン参加者を前提に採用を進めていることもあるため、業界によって参加の必要性が変わる点には注意が必要です。
参加で得られるもの/得られないこと
インターンに参加することで得られるものはたくさんあります。具体的には以下のようなものです。
- 実際の業務や社風を体感できる
- 社員との接点を通じてリアルな情報が得られる
- 就活で使える自己PRのネタができる
- 面接の練習や場慣れにつながる
とくに、志望業界がまだ定まっていない場合は、インターンを通じて業界の向き不向きを体感できるのは大きなメリットです。
一方で、インターンに行ったからといって、必ずしも本選考が有利になるとは限りません。企業によってはインターン参加者と一般応募者を分けずに選考するところもあり、参加の有無だけでは差がつかない場合も多くあります。また、短期インターンでは実務体験がほとんどできず、「説明会に毛が生えた程度」の内容になることもあります。
最も大切なのは、インターンに行くかどうかよりも、「どう就活に活かすか」です。「行かなかったからダメ」ではなく、「行ってどうだったか」「行かずにどう準備したか」が問われるのが現代の就活です。
まずは焦らず、自分にとって必要かどうかを考えてみてください。参加する場合も、「なんとなく参加する」のではなく、目的意識を持って臨むことが、納得のいく就活につながります。
インターンの基本とよくある誤解

インターンに参加するか迷っている就活生にとって、「そもそもインターンとは何か?」をきちんと理解することは重要です。言葉の意味があいまいなまま進んでしまうと、目的に合わないプログラムを選んでしまったり、期待はずれの経験になることもあります。ここでは、インターンとインターンシップの違い、制度の内容、そして報酬面について整理していきます。
インターンとインターンシップの違い
就活の情報を調べていると、「インターン」と「インターンシップ」という言葉が入り混じって使われていることに気づくと思います。結論から言えば、この2つに明確な違いはなく、どちらも学生が企業の現場に入り、一定期間業務を体験する取り組みを指します。
ただし、ビジネスの現場では、ややニュアンスの違いがあります。
- 「インターン」は短期・体験型の意味合いが強い
- 「インターンシップ」は制度として整備された長期の実務型を指すことが多い
たとえば、ある学生が参加した広告会社の5日間インターンでは、実務というよりも講義や会社紹介が中心でした。一方、同じ会社の3か月間のインターンシップでは、実際にチームに配属され、SNS広告の運用を担当していたそうです。
インターンとはどんな制度?
インターンは企業が学生に対して仕事体験の機会を提供する制度です。文部科学省で「インターンシップ=就業体験」と定義しており、企業理解を深めることが目的とされています。
インターンは以下の3つに分類できます。
| 種類 | 期間 | 特徴 |
|---|---|---|
| 短期型 | 1日〜数日 | 業界説明やグループワークが中心 |
| 中期型 | 1週間〜1か月 | 実務体験あり、報酬はないことが多い |
| 長期型 | 数か月以上 | 実際の業務を行うことが多く報酬あり |
制度として明確なルールはないため、企業ごとに内容が大きく異なるのも特徴です。そのため、「インターン=企業体験」という言葉だけで判断せず、内容をよく確認することが重要です。
有給・無給の違いや報酬の目安
インターンには有給と無給があります。とくに短期インターンは、報酬が出ないケースがほとんどです。一方で、長期インターンでは時給1,000円〜1,500円程度の報酬が支払われることもあります。
例えば、あるWeb系スタートアップでは、週3日以上出勤できる学生に対して時給1,200円を支払う長期インターンを実施しています。業務内容はライティングやSNS運用で、就活後もその経験が活かせるとのことでした。
ただし、有給かどうかにこだわるよりも、「そこでどんな経験ができるのか」「就活にどうつながるか」を重視した方が、自分にとって意味のあるインターンになるでしょう。
制度や言葉の違いにとらわれすぎず、まずは自分に合った内容を選びましょう。次に参加する時期や準備について考えてみるのもおすすめです。
参加するならいつから?スケジュールと準備

インターンに参加したいと思ったとき、次に気になるのは「いつから動けばいいのか」という点です。早く始めすぎて空回りしたくはないし、出遅れて焦るのも避けたいところ。ここでは学年ごとの目安や就活全体とのバランス、実際のエントリーまでの流れについてわかりやすく解説します。
学年別の始めどき
インターンは学年によって参加の仕方が異なります。以下のようなイメージをもっておくと安心です。
- 大学1・2年生:キャリア形成の入り口。長期インターンで実務経験を積む人も増えていますが、無理に参加しなくてもOK。学業やサークルとの両立が前提になります。
- 大学3年生:インターン参加のピーク。特に夏(7〜9月)と冬(12〜2月)に多くの募集が集中します。選考直結型インターンも増えるため、本選考の一環として意識して動く必要があります。
- 大学4年生:基本的には本選考に集中する時期。ただし、内定後や卒業後の長期インターンも一部で存在しています。
「早く動いたほうがいい」と言われる理由は、行動量より“行動経験”の積み重ねがカギになるからです。たとえば、3年生の夏に1社でもインターンを経験しておくと、冬以降の動き方や業界理解がぐっと深まります。
就活とのバランスを考えるポイント
インターンに集中しすぎて、肝心の本選考の準備が疎かになる学生は少なくありません。とくに長期インターンは拘束時間が多いため、学業・バイト・資格勉強などとの両立が難しくなることも。
バランスを取るには、次のようなポイントを意識しましょう。
- 時間管理を徹底する(スケジュールアプリ活用など)
- 「目的のあるインターン」に絞る(なんとなく参加はNG)
- 短期と長期を組み合わせて計画を立てる
たとえば、ある学生は夏に短期インターンを3社回り、冬は1社の長期インターンに集中しました。これにより、比較対象が増え、志望業界を早めに決めることができたそうです。
エントリーから参加までの流れ
インターンへの参加は、以下のようなステップで進んでいきます。
- インターン情報を収集(就活サイト、SNS、大学など)
- エントリーシートを提出
- 書類選考・適性検査などの審査を受ける
- 面接やグループワークへの参加(企業による)
- 合格通知を受けて参加確定
企業によっては「先着順」や「選考なし」のインターンもありますが、人気企業ではエントリー時点で倍率が高く、早期の情報収集と応募が必須です。
就活はタイミングがすべてではありませんが、「いつ動き出すか」で差がつくのも事実です。無理のない範囲で、興味のある企業に一歩踏み出してみるところから始めてみてください。
インターンの種類と選び方

インターンにはさまざまな形式があり、それぞれにメリットと注意点があります。どのタイプを選ぶかは、自分の目的やスケジュール、興味関心によって変わります。ここでは、主なインターンの種類と、それぞれの特徴、そして自分に合った選び方を具体的に見ていきましょう。
短期・長期・オンラインの特徴
インターンは主に「短期」「長期」「オンライン」の3つに分けられます。
- 短期インターン(1日〜2週間程度)
説明会に近い形式のものもあり、グループワークや業界紹介が中心です。複数社を比較したい人や、まだ志望業界が定まっていない人に向いています。 - 長期インターン(3か月〜半年以上)
実務に関わる機会が多く、社員と同じように業務を経験できます。Web企業やベンチャー企業では長期型を採用しているケースが多く、スキルを身につけたい人や将来の選択肢を広げたい人に人気です。 - オンラインインターン
Zoomなどを活用し、自宅から参加できる形式です。場所に縛られずに参加できるため、地方在住者や学業が忙しい人にも好評。ただし、実務体験というより情報提供型が多くなりがちです。
自分の目的に合った形式を選ばないと、「思っていたのと違った」というミスマッチが起こりやすいため、事前に内容をよく確認することが大切です。
自分に合った探し方
インターンを探す際に最初にやってしまいがちなのが、「有名企業から見ていく」ことです。しかし、実際には自分の性格や生活スタイルに合うかを重視して探すほうが、満足度の高い経験につながります。
おすすめの探し方は以下の通りです。
- 就活サイト(リクナビ、マイナビなど)を活用
- 大学のキャリアセンターで相談
- SNSやOB・OG訪問でリアルな情報を収集
- 自分の興味キーワードでGoogle検索(例:「食品 インターン 東京」)
とくに最近は動き出す時期が早まっているので、夏前の情報収集がカギになります。
興味分野で選ばなくてもOK?
「自分の興味ある分野がまだわからない」と感じている人も多いでしょう。実は、インターンは“興味があるかどうか”で選ばなくても問題ありません。むしろ、「あえて興味のない業界に飛び込んでみたら、思いがけず面白かった」というケースはよくあります。
たとえば文系の学生が、IT企業のインターンに参加して「現場の雰囲気がよくて意外と向いているかも」と進路を変えることも珍しくありません。
つまり、「向いている・向いていない」や「好き・嫌い」は、体験して初めてわかることなのです。だからこそ、インターンの段階では興味の幅を広げる気持ちで参加してみてください。
まずは、自分の行動が新しい選択肢を生み出すと考えて、気軽に一歩を踏み出してみましょう。
就活にどう活かす?経験の使い方

インターンに参加する目的のひとつは、将来の就職活動で「使える経験」を得ることです。ですが、ただ参加するだけでは意味がありません。重要なのは、そこで得たことをどう自分の言葉に変え、面接やエントリーシートで伝えるか。ここでは、アピール方法や、未経験でも問題ない理由、そして経験の振り返り方を紹介します。
面接やエントリーシートでのアピール方法
インターン経験を効果的に伝えるには、「なにをしたか」よりも「どう考えて行動し、なにを学んだか」に焦点を当てることがポイントです。たとえば「営業同行をした」だけでは他の応募者と差がつきませんが、
「営業先で社員が信頼を得る過程を観察し、“相手目線の提案”の大切さを実感しました。そこから逆算してプレゼン練習を繰り返し、自分でもロールプレイで成果が出せました」
のように、気づきと行動をセットで語ると、説得力が増します。
エントリーシートでも同様で、「何をやったか」の報告で終わるのではなく、「その経験から何を学び、どう活かしたいか」を明確にしましょう。STAR法を意識すると、構成が自然で読みやすくなります。
STAR法とは、自分の経験をわかりやすく伝えるための4つの流れのこと。
Situation(状況)、Task(課題)、Action(行動)、Result(結果)の頭文字を取ったフレームワークです。
- S(Situation)=状況
→ どんな場面だったかを説明します。 - T(Task)=課題
→ 自分がやるべきこと・目標を伝えます。 - A(Action)=行動
→ その課題にどう取り組んだかを話します。 - R(Result)=結果
→ 行動の結果どうなったかを伝えます。
この順番で話すと、伝わりやすくて評価されやすくなります。
インターン未経験でも大丈夫
「インターンに行ってないけど、もう就活始まる…」と焦っている人も大丈夫です。実際、企業が重視しているのは“インターンの有無”より“その人がどんな視点で行動してきたか”です。
アルバイト、ゼミ、ボランティアなど、日常の中にもアピール材料はたくさんあります。ある学生は、飲食店のバイトで「新人教育マニュアルを自作し、スタッフの離職率を下げた」エピソードを語り、複数社から高評価を得ました。
つまり、インターンは就活の“必須条件”ではなく、“ひとつの選択肢”にすぎません。大切なのは、自分の経験を振り返り、相手に伝わる言葉で整理することです。
経験を振り返って次に活かす
インターンが終わったら、それでおしまいにせず、必ず「振り返り」を行いましょう。記憶が新しいうちに以下のようなことを書き出しておくと、エントリーシートや面接対策に活かせます。
- 印象に残った場面
- そのとき自分がどう考えて行動したか
- 難しかったこととその乗り越え方
- 学んだことと今後への応用
このプロセスを通じて、「自分に向いている仕事の傾向」や「強み・課題」がクリアになります。また、面接で深掘りされたときに迷わず答えられるようになります。
インターンに参加したかどうかではなく、“どう受け止めて、どう次につなげるか”が本当の差になります。経験を味方にできるよう、自分の中で整理しておきましょう。
よくある質問
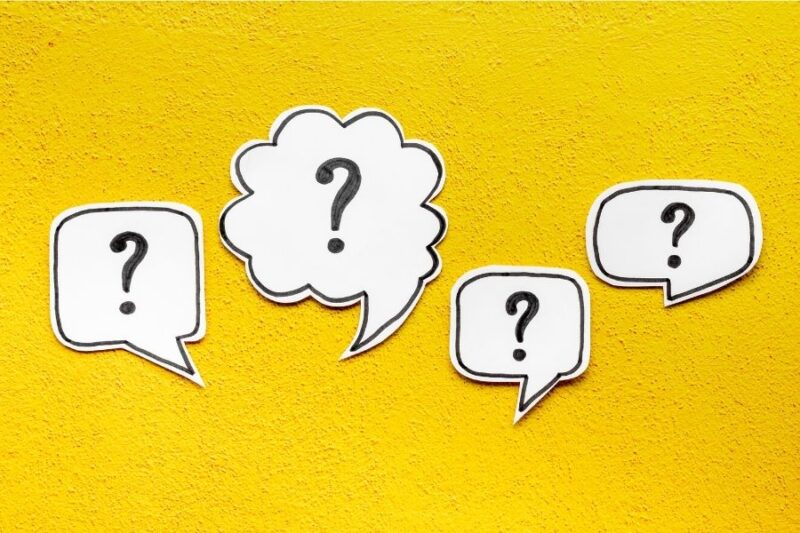
Q. 就活でインターンに参加しないとどうなる?
インターンに参加しなくても就活で不利になるわけではありません。ただし、企業研究や自己分析の機会が減るため、志望動機が浅くなったり、本番の面接で話すネタが少なくなる傾向があります。経験の差よりも「どう準備するか」が重要ですので、他の活動で補う意識が大切です。
Q. 就活でインターンシップに参加するメリットは?
インターンに参加することで、企業や業界のリアルな姿を知ることができ、自分の向き・不向きを見極めるヒントになります。また、職場の雰囲気や働き方を体験できるため、志望動機に説得力が出るほか、企業によっては本選考に有利になるケースもあります。
Q. 大学3年生でインターンに行かない割合はどのくらいですか?
文部科学省の調査などでは、大学3年生の約6〜7割が何らかのインターンに参加しているとされています。裏を返せば、3〜4割は参加していないことになります。必須ではありませんが、参加者が多数派になってきているのは事実です。
Q. インターンシップに行った方がいい理由は何ですか?
インターンは業界理解や職種理解を深めるのに最適な手段です。単なる会社説明会とは異なり、実際の業務や社員と触れることで、自分に合った企業像が明確になります。また、場慣れや自己分析にもつながり、本番の就活でも自信を持って臨めるようになります。
Q. インターンシップに行ってない人の割合は?
大学生全体で見ると、インターン未経験者は約3〜4割程度です。特に理系や専門職志望者、地方大学の学生は、参加率にばらつきがあります。インターンに参加していなくても、本選考にしっかり向き合えば十分にチャンスはあります。
Q. 大学3年生はインターンに何社くらい参加するのがいいですか?
目安として、短期インターンなら3〜5社、長期インターンなら1〜2社がバランスのよい参加数です。大切なのは数ではなく「目的意識」。興味のある業界や企業を比較できる程度に複数参加し、自分の視野を広げることを意識しましょう。
インターンに参加するかどうかは、目的や状況によって正解が異なります。この記事が、自分に合った選択を見つけるヒントになれば幸いです。就活は一人ひとりのペースで進めて大丈夫です。

お問合せや資料請求はこちらから
▶︎ サムライカレーSDGs 資料請求、お問合せ
個別オンライン説明会の前に動画みたい方