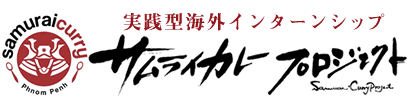総合型選抜の志望理由書の書き方に悩む高校生へ。合格者が実践した構成の作り方や表現の工夫、面接まで一貫した内容に仕上げるコツを専門家が分かりやすく解説します。読み終わるころには、自信を持って自分らしい志望理由書を書き始められます。
まず確認!総合型選抜で合格する志望理由書とは

総合型選抜で求められる志望理由書は、単なる「志望動機」ではありません。高校生活での学びや経験、自分の将来像、大学での学びとの接点を一貫性のあるストーリーとして伝える力が求められます。ここでは、まず総合型選抜がどのような入試か、そして志望理由書に大学が何を期待しているのかを理解するところから始めましょう。
他の入試との違い
総合型選抜は、学力試験だけでは測れない「人物評価」に重きを置いた入試です。たとえば、学校推薦型選抜では評定平均など一定の基準がありますが、総合型選抜ではその枠にとらわれず、自己PRや課外活動の実績、将来への意欲など、より多面的に評価されます。
特に注目すべきは、志望理由書と面接の一貫性。学力の点数よりも、「なぜこの大学なのか」「将来どんな姿を目指しているのか」といった深い問いに自分の言葉でしっかり答えられるかがカギになります。
大学が志望理由書で本当に見ているポイント
大学が志望理由書で重視するのは、次の3点です。
- 目的の明確さ:「大学で何を学びたいのか」が具体的に書かれているか
- 適合性:大学のカリキュラムや方針と、自分の興味・目標がどれほど一致しているか
- 主体性と将来性:自ら行動し、将来の展望を持っているかどうか
たとえば、「心理学を学びたい」と書くだけでは不十分です。「高校での人間関係の悩みを通して心の仕組みに関心を持ち、○○大学の○○ゼミで学びを深めたい」と書くことで、説得力が一気に増します。
書き始める前に知っておくべきこと
志望理由書は、いきなり書き始めるものではありません。まず必要なのは「自己分析」と「大学研究」です。以下のような準備が不可欠です。
- 自分が熱中した活動や経験を書き出す
- 大学のアドミッションポリシー(求める学生像)を確認する
- オープンキャンパスや模擬講義に参加し、学部の雰囲気を知る
また、書き始めの段階で「文字数制限(例:800字)」を意識することも大切です。限られた文字数の中で、最も伝えたいことを整理する力が求められます。
総合型選抜の志望理由書は、自分の過去・現在・未来を一本の線でつなぎ、大学という舞台で何を実現したいのかを言語化する場です。まずは、自分自身と真剣に向き合い、大学との接点を明確にするところからスタートしてみましょう。
志望理由書の正しい書き方ステップ

合格を勝ち取る志望理由書には、単なる思いつきではなく、準備・構成・言葉選びの工夫が必要です。ここでは高校生が実践しやすい書き方の流れと、文の組み立て方を具体的に紹介します。文章の骨組みを整えることで、面接官に伝わる「読ませる志望理由書」に近づけます。
高校生がやるべき事前準備
書き始める前に、必ずしておきたいのが「自己分析」と「大学研究」です。たとえば、部活動で感じた達成感や、学校行事で得た学びなど、自分の経験を棚卸しすることで、書くべきテーマが見えてきます。
また、大学のアドミッションポリシーやカリキュラム、教授の専門分野を調べておくことも重要です。ある受験生は、「ゼミの先生が研究している○○に関心がある」と書いたことで、面接時に深く話が広がりました。
チェックリスト例:
- 自分の強み・価値観は?
- なぜこの大学・学部を選んだ?
- 高校生活で努力したことは?
書き出しで差がつく!読まれる第一文とは
「私は将来、人の心に寄り添う仕事がしたいと思っています。」――ありがちな書き出しでは印象に残りません。書き出しは、あなたの志望理由書が「読まれる」かどうかを決める最初の勝負どころです。
コツは、エピソードや具体的な出来事から始めること。たとえば、「中学時代に不登校を経験した私は、心理学に強い関心を抱くようになりました。」という一文であれば、自然と続きを読みたくなります。
第一文では以下を意識:
- 自分にしかない体験を書く
- 感情や場面の描写を入れる
- 結論は後半で示す
本文の構成テンプレート(800字対応)
800字の志望理由書では、無駄のない構成が重要です。以下のような4段構成が効果的です。
| 段階 | 内容 | 文字数目安 |
|---|---|---|
| 導入 | 印象的な体験や出会い | 約150字 |
| 動機 | その経験から大学志望へ至った理由 | 約250字 |
| 適合性 | 大学でどう学びたいか、具体的に | 約250字 |
| まとめ | 将来像と大学での学びのつながり | 約150字 |
この枠組みに沿って書けば、ストーリーに流れが生まれ、説得力が増します。
推薦者や家族の意見は入れていいのか?
志望理由書は「あなた自身」の考えを書く場所です。ただし、推薦者や家族の言葉がきっかけになった場合は、その一部を引用しても問題ありません。
たとえば、「進路に悩んでいた時、担任の先生に“君の強みは人を動かす力だ”と言われ、自分の特性を見つめ直しました」と書くことで、内省のプロセスを具体的に伝えることができます。
ただし注意したいのは、他人の言葉だけで動機が構成されている場合。自分の意志や行動が伴っていないと、説得力は一気に薄れてしまいます。
準備から構成までを丁寧に積み重ねることが、合格へと近づく大きな一歩になります。次は、大学にしっかり伝わる内容づくりに進んでいきましょう。
大学に刺さる内容の作り方

志望理由書で合否を分ける最大のポイントは、「大学に刺さる内容かどうか」です。ここでは、大学・学部の魅力をどう具体的に捉え、自分の経験とどうつなげていくか、その作り方を解説します。ただ「この大学に行きたい」だけでは不十分。説得力ある動機を構築するには、深い分析とリアルな体験が必要です。
志望動機の深掘り(なぜこの大学・学部?)
受験生の多くが「興味があるから」「有名だから」といった浅い理由で終わりがちです。しかし、大学側はその先を見ています。たとえば、福祉系の学部を志望する高校生が「地域の高齢者ボランティアに参加した経験から、制度や支援の仕組みに疑問を持った」と書けば、動機の背景に厚みが出ます。
深掘りのポイント:
- 「何に疑問を持ったか」
- 「なぜそれが気になるのか」
- 「どの学びが解決につながるのか」
つまり、動機には“きっかけ→疑問→行動→学び”という流れがあると、自然と説得力が生まれるのです。
オープンキャンパス・教授・カリキュラムとの接点の書き方
実際に見聞きしたことを書くと、志望理由は格段に強くなります。たとえば、「オープンキャンパスで○○教授の講義を聞き、障害児教育の最前線に触れた」「社会調査の実習に興味を持ち、○○ゼミでの学びに惹かれた」といったように、自分がどう感動し、どう考えたかを交えて書きましょう。
活用できる接点:
- オープンキャンパスや模擬講義の体験
- 教授の著書や研究テーマ
- 学部の実習・演習・ゼミ制度
ここで重要なのは、“見た”だけで終わらせず、“なぜそこに惹かれたのか”を自分の言葉で伝えることです。
自分の経験・エピソードとの一貫性を持たせるコツ
せっかく大学について詳しく書いても、それが自分の人生や価値観とつながっていないと空回りしてしまいます。たとえば、「新聞部での取材活動を通じて、社会問題を深く掘り下げる力を養った。これを○○学部でさらに発展させたい」というように、経験と学びたい内容が地続きになっていることが大切です。
一貫性を持たせる方法:
- 過去の経験 → 学びたい内容 → 将来像 の流れを意識する
- 書き出した内容に「なぜ?」を3回繰り返して掘り下げる
- 時系列で振り返りながら、自分の成長を言語化する
文章に一貫性があると、読み手は自然に納得できます。そして何より、「この人は自分の人生を自分で考えている」と伝わるのです。
大学に刺さる内容をつくるには、手間を惜しまない姿勢と、自分の経験に対する深い理解が欠かせません。次に書くときは、思いつきでなく、準備を重ねた“本気の志望動機”を目指しましょう。
NGワード・落ちる志望理由書の特徴とは?

せっかく内容を練っても、伝え方ひとつで大きく減点されることがあります。志望理由書では、「どう書くか」だけでなく「何を書いてはいけないか」も重要です。ここでは、実際に多くの高校生がやりがちなNG表現とそのリスク、改善のヒントを紹介します。よくあるミスを知っておくことで、合格にぐっと近づきます。
抽象的すぎる表現
「人の役に立ちたい」「国際的な視野を広げたい」――一見前向きな言葉ですが、内容があいまいだと評価されにくくなります。たとえば、「ボランティア活動に興味がある」という表現だけでは、具体性が足りません。どんな活動で何を感じたのか、どこに課題を見出したのかまで書き込むことで、ようやく伝わるものになります。
NG例:
- 社会に貢献したい
- 知識を深めたい
- 自分を成長させたい
→改善:どんな場面でその思いが生まれたのかを、具体的な体験とセットで書く
「すごい」「役に立ちたい」などのありきたりな表現
「すごい先生がいると聞いた」「この学部は役に立ちそう」などの表現は、語彙が乏しく説得力に欠けます。また、「なんとなく良さそう」という印象を与え、受験生としての主体性が見えなくなります。
同じ思いでも、少し表現を工夫するだけで印象は大きく変わります。たとえば、「○○教授のゼミでは、災害時の心理的ケアを扱っており、自分が中学生のときに被災した経験と重なりました」といったように、自分の背景と結びつけることで深みが出ます。
大学の公式情報の丸写し
「本学は先進的なカリキュラムを提供しており…」というような、パンフレットそのままの文章は絶対に避けるべきです。こうした表現は、大学のことを調べたようで、実は中身が空っぽに見えてしまいます。
たとえば、「福祉実習が充実している」という情報を使うなら、「実際にオープンキャンパスで○○実習室を見学し、現場と連携した実践型の学びに魅力を感じた」と書くことで、自分の体験や気づきが加わり、説得力が出ます。
面接と矛盾する内容
「志望理由書ではAと書いていたのに、面接ではBと話した」――これは面接官が最も不信感を持つパターンです。たとえば、志望理由書で「研究職を目指したい」と書きながら、面接では「企業で働きたい」と話してしまえば、準備不足を疑われます。
志望理由書と面接内容は一貫している必要があります。特に「将来像」「学びたいこと」「大学の魅力」を明確に揃えることで、面接官の納得感が高まります。
書いてはいけない表現には、共通して「自分の言葉がない」という特徴があります。今一度、あなたの志望理由書を読み直し、「その言葉、本当に自分の気持ち?」と問いかけてみてください。違和感があるなら、それは改善のチャンスです。
書き終えたらココをチェック!提出前の最終確認

どれだけ中身が素晴らしくても、最後の仕上げが雑だと、志望理由書は力を発揮しきれません。誤字脱字や表現の曖昧さ、小さな矛盾が命取りになることもあります。ここでは、提出前に必ず確認すべきポイントを3つに分けて紹介します。合格に近づくために、最後まで丁寧に見直しましょう。
推敲チェックリスト
書き終えたら、まずは冷静に見直すことが大切です。内容がまとまっているかだけでなく、文章として読みやすいかを確認しましょう。以下は、受験生がよく見落としがちなチェック項目です。
提出前に確認したい10項目:
- 文字数制限を守っているか(例:800字以内)
- 文末表現が単調になっていないか(「〜です。〜です。」の繰り返し)
- 同じ言葉を何度も使っていないか
- 一文が長くなりすぎていないか
- 大学名・学部名に誤りはないか
- 主語と述語が正しく対応しているか
- 自分の体験が具体的に書かれているか
- アドミッションポリシーとズレていないか
- 面接で聞かれて困るような内容はないか
- 読み手を意識した構成になっているか
特に「自分では読めてしまう」部分ほど注意が必要です。
声に出して読む・他人に読んでもらう効果
自分の目だけで確認していると、文章の“違和感”に気づきにくいものです。そんなときは、声に出して読むことが効果的です。読みにくい箇所や、主語と述語のねじれ、文のリズムの悪さがすぐに分かります。
また、信頼できる人(先生・家族・先輩など)に読んでもらうことも大きなメリットです。第三者の視点で「ここは意味が分かりづらい」「この表現、薄いかも」といったフィードバックがもらえるからです。
ある生徒は、担任の先生に「この文、なんとなく浮いてるよ」と指摘され、そこを修正したことで読みやすさが格段に上がりました。
いつ提出すべき?出願スケジュールの基本
志望理由書はギリギリで出せばいい、というものではありません。出願日から逆算して、最低でも2週間前には完成させることをおすすめします。
スケジュール管理のポイント:
- 出願締切日を確認し、学校に提出する日を把握する
- 推薦書など他の書類との兼ね合いを考慮する
- 推敲と第三者チェックに1週間以上確保する
また、学校によっては事前にチェックを受ける必要がある場合もあるので、担任や進路指導の先生との連携も忘れずに。
「これで完璧」と思っても、最後のチェックで見つかる改善点は意外と多いものです。提出前のひと手間が、あなたの志望理由書を“読み飛ばされない文章”へと引き上げてくれます。仕上げの丁寧さこそ、合格への一歩です。
実際の例文で学ぶ!成功する志望理由書の実例集

「どう書けばいいのか分からない」と悩む受験生にとって、具体的な例文は最高のヒントになります。ここでは、800字以内でまとめられた高校生向けの例文や、大学ごとの特徴を押さえたAO入試対応の文例、そして実際に合格した先輩たちの志望理由書から学べるポイントを紹介します。ただマネをするのではなく、「なぜこの表現が伝わるのか」を意識しながら読みましょう。
志望理由書 例文(800字・高校生向け)
以下は、心理学部を志望する高校生の例文です。文字数は約790字。体験→興味→大学での学び→将来像へと自然につながっています。
中学生の頃、不登校の友人がいました。私はその子を励ましたい一心で毎日連絡を取り続けましたが、何もできない自分に無力感を覚えました。この経験がきっかけで、人の心に寄り添う仕事がしたいと強く思うようになりました。
高校では、生徒会活動や地域ボランティアに積極的に参加しました。特に高齢者施設での活動では、話を聞くだけで表情が和らぐ場面に何度も立ち会い、「聞く力」の大切さを実感しました。
貴学の心理学部では、実践的なカウンセリング演習に力を入れている点に魅力を感じています。また、○○教授の「対人援助スキル」の講義では、理論と実践のバランスを学べると知り、自分の学びたい内容と重なりました。
将来は、スクールカウンセラーとして子どもたちの心のサポートを行いたいと考えています。そのために、まずは大学で心理学の基礎から実践までをしっかり学びたいです。
このように、文字数に収めつつ、感情と事実をバランスよく書くことが大切です。
志望理由書 例文(大学別・AO入試対応)
大学によって求められる人物像や評価ポイントは異なります。たとえば、国際系の学部では、英語学習の熱意だけでなく、国際社会に対する視点や課題意識を盛り込むと効果的です。
AO入試向けの例文では、以下のような構成が有効:
- 自分が向き合ってきた社会課題(例:外国人児童の教育格差)
- その課題に対する自分なりの行動や視点
- 大学でどんな知識やスキルを学びたいか
- 卒業後にどう活かしたいか
志望理由書では、「知りたい・学びたい」だけでなく、「なぜ今、自分がその学びを必要としているのか」まで説明できると説得力が増します。
成功した先輩の例文から学ぶポイント解説
実際に合格した先輩の志望理由書を読むと、意外なほど“普通の言葉”で書かれていることに気づくはずです。特別な経験がなくても、等身大の自分をどう表現するかが鍵になります。
成功例に共通するポイント:
- 「私は〜と感じました」など、自分の言葉で語っている
- 教科書的な表現よりも、体験に根ざした言葉を使っている
- 一貫して“本人らしさ”が伝わってくる
模倣ではなく、読み手に「この人に会ってみたい」と思わせる文章にすることが大切です。
例文を読むときは、「自分だったらどこに書き換えるか」を意識してみてください。その視点が、あなただけのオリジナルな志望理由書づくりの第一歩になります。
面接を見据えた志望理由書の活用法
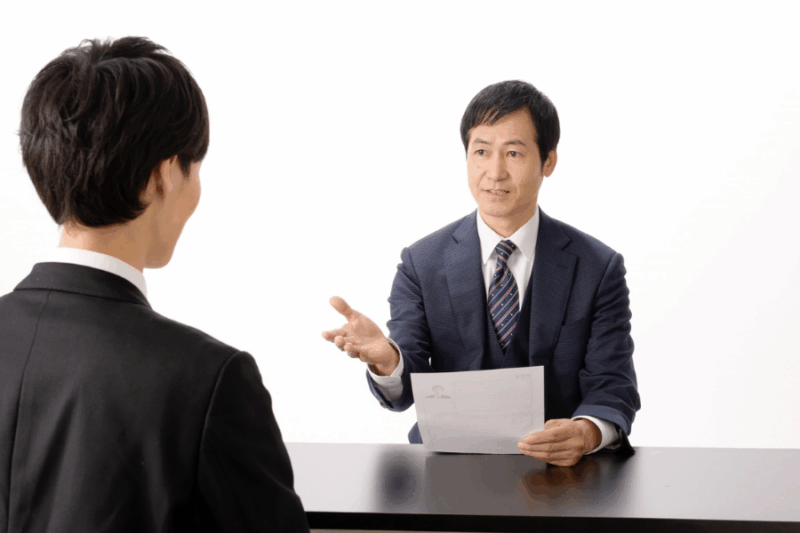
総合型選抜では、書類審査と面接の両方が評価対象になります。特に志望理由書は、面接の“質問の種”として使われることが多く、書き方ひとつで面接の雰囲気が大きく変わります。ここでは、面接を意識した志望理由書の書き方と、一貫性を保つための工夫、さらには深掘り質問を受けたときの対策までを具体的に紹介します。
7-1. 面接官が質問しやすい志望理由書とは
読み手が「この子と話してみたい」と思える志望理由書には、適度な余白と問いのヒントがあります。すべてを説明しきらず、「なぜそう思ったのか?」と掘りたくなるような文の残し方が理想的です。
たとえば、「ボランティア活動で地域との関わりに関心を持った」と書くだけでなく、「特に印象的だったのは、ある高齢者との出会いでした」といった“続きが気になる書き方”が、質問を引き出します。
ポイント:
- 読み手が疑問を持つ余地を残す
- 感情や行動の変化を書く(→質問しやすい)
- 事実だけでなく“なぜ”や“どうして”を含める
志望理由書と面接内容の一貫性を保つ方法
面接では、志望理由書の中にある内容がそのまま話題になります。そのため、書いた内容と実際の受け答えがズレてしまうと、評価が一気に下がってしまいます。
一貫性を保つための対策:
- 書いた内容を自分の言葉で話す練習をする
- 模擬面接で質問されそうな部分を重点的に準備する
- 志望理由書の内容を「要点だけで3分で話す」と決めて練習する
ある生徒は、書類では「心理学に興味がある」と書いていたものの、面接で「福祉系にも関心があって…」と話してしまい、焦点がぼやけてしまいました。ひとつの軸を中心に話すことで、信頼感が生まれます。
面接で深掘りされやすいポイントの仕込み方
面接官が注目するのは、“あなたの経験”と“そこから得た学び”です。つまり、志望理由書の中にあらかじめ「深掘りされやすい種」を入れておくことで、会話が自然に広がります。
例:
- 「文化祭でリーダーを務めた経験」→「どんな場面で苦労した?」
- 「オープンキャンパスで○○教授の話に共感」→「どこに共感したのか?」
- 「将来は○○の分野で活躍したい」→「その分野に入ったきっかけは?」
こうした部分を、文章中に1〜2か所“あえて深く書かず”に配置するのがコツです。読み手が「詳しく聞きたい」と思ったところから、面接がスムーズに進んでいきます。
面接と志望理由書は、別々ではなく“連動した一つの評価軸”です。だからこそ、書くときから「どこを聞かれるか」を意識しておくことが、合格への大きな差になります。書類を書き終えたら、一度“話せるか”という視点で読み直してみてください。
よくある質問

- 志望理由書でNGな書き方は?
-
NGな書き方の代表例は、抽象的な表現やありきたりなフレーズの多用です。「人の役に立ちたい」「学びを深めたい」だけでは動機が弱く、面接官の印象に残りません。また、大学の公式サイトの内容をそのまま写すのも避けるべきです。自分の体験や考えを交えて、オリジナルな内容にすることが大切です。
- 志望理由書の書き方、はじめにはどう書けばいいですか?
-
はじめの一文は、読んでもらえるかどうかを左右する重要な部分です。効果的なのは、自分の体験や出会いからスタートすることです。たとえば「中学生のときに地域の福祉活動に参加し、ある出来事がきっかけで〜」と書くと、関心を引きやすくなります。結論から入るより、感情に訴える始まりが効果的です。
- 総合型選抜で落とされる理由は何ですか?
-
総合型選抜で不合格になる大きな理由は、「大学とのミスマッチ」です。志望理由が浅く、学部の学びと結びついていないと、評価されません。また、志望理由書と面接内容が矛盾していると「準備不足」と判断されることも。その他、提出書類のミスや自己分析の甘さも、不合格の原因となります。
- 総合型選抜の志望理由書の文字数は?
-
大学や学部によって異なりますが、総合型選抜の志望理由書はおおむね600字〜800字で指定されることが多いです。一部の大学では400字や1,000字などのパターンもあるため、必ず募集要項で確認しましょう。字数に合わせて内容を取捨選択し、伝えたいことを的確にまとめる力も評価対象になります。
- 志望理由としてダメな例は?
-
「親に勧められたから」「なんとなく興味がある」「偏差値がちょうどよかった」など、本人の主体性が感じられない理由はNGです。また、「有名な大学だから」など漠然とした志望動機も印象が悪くなります。大学で何を学びたいか、将来にどう活かしたいかという視点がないと、説得力に欠けます。
- 志望理由書で「思いました」の言い換えは?
-
「思いました」は使いすぎると幼く聞こえるため、他の表現に置き換えるのが効果的です。たとえば「感じました」「気づきました」「強く意識するようになりました」「考えるようになりました」などがあります。場面によって「痛感しました」「実感しました」と感情の深さを表すのもおすすめです。
総合型選抜の合否を左右する志望理由書は、準備と構成がすべてです。この記事を活用し、自分の言葉で伝える一通を完成させてください。納得の結果にきっとつながります。